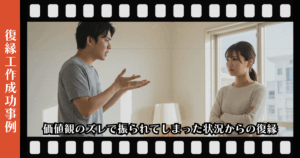復縁屋ハートリンクで実際に対応した案件の一部を、依頼者様のご了承をいただいたうえで掲載しています。なお、プライバシー保護のため、内容の一部は編集を加えております。
| 工作種別 | 復縁工作 |
|---|---|
| 依頼者情報 | 千葉県在住36歳 女性 |
| 対象者情報 | 千葉県在住37歳 男性 |
| 契約期間 | 5カ月 |
参考記事:復縁診断|復縁したい!あなたの復縁の可能性を測ります。
ご相談
今回ご相談に来られたのは、千葉県内にお住まいの30代の女性でした。
ご主人とは10年以上結婚生活を続けており、小学生のお子さんがいらっしゃいます。
穏やかで温かい家庭を築いてこられたとのことでしたが、半年ほど前から夫婦関係に変化が生じ、現在は別居状態となっています。
きっかけは、依頼者様がご主人の生活の変化に気づいたことでした。
以前は休日に家族で過ごす時間が多かったものの、ここ数か月は「勉強会がある」「自分を見つめ直したい」と言って外出することが増え、週末はほとんど家を空けるようになっていたそうです。
浮気をするような方ではないようで、当初は自己啓発のような活動だと思い、特に強くは止めなかったものの、次第に家族との会話が減り、子どもと触れ合う時間も極端に少なくなりました。
ある日、依頼者様が「最近、どこで何をしているの?」「浮気でもしているんでしょ?」と問いかけた際、ご主人は強い口調で反発されました。
「何も知らないくせに口出しするな」「俺のことを分かりもしないくせに」と、もともと穏やかな性格だったようで初めて怒鳴りつけられたとのことでした。
そのやり取りをした数日後、唐突にご主人は荷物をまとめて家を出て行かれたとのことです。
その際には「生活費は入れる、探すな」と言われたとのこと。
以後、連絡はほとんど途絶え、実家にも顔を出さず、付き合いのある夫の同僚から「宗教に関わっているらしい」という話だけが耳に入ったといいます。
依頼者様は、「まさか自分の夫が宗教にのめり込むなんて」と強い衝撃を受けておられました。
「どうして止められなかったのか」「あの時、もっとちゃんと向き合っていれば」と自責の念を口にされ、今も連絡の取り方さえ分からない状態が続いています。
また、義両親にも相談されたそうですが、「本人が決めたことだから」と言われてしまい、家庭としての繋がりも途絶えてしまったとのことでした。
依頼者様は、宗教そのものに偏見があるわけではなく、夫が信仰を持つこと自体を否定したいわけでもありません。ただ、家族を顧みず、子どもの成長の節目にも姿を見せない現状に、どうすればいいか分からないという切実な思いを抱えておられました。
「彼が変わってしまったように見えるけれど、本当は戻ってきてほしい」
その一点だけは、面談中もはっきりとした口調で何度も繰り返されていました。
弊社へのご相談は、「宗教が原因で夫婦が別れたのかもしれない」という前提でのものでした。
依頼者様の中では、夫が見知らぬ思想や団体に取り込まれてしまったという恐怖と、それでも家族として支え直したいという希望が入り混じった複雑な心境が見て取れました。
面談・提案
依頼者様のご相談内容を整理した段階で、我々が最初に着目したのは、状況の把握が断片的であるという点でした。
依頼者様は「宗教が原因で夫が出て行った」と考えておられましたが、その根拠は同僚の噂や、ご主人の曖昧な発言にとどまっていました。
ご本人が直接「宗教に入った」と語ったわけではなく、また特定の団体名や活動実態も分かっていない状態でした。
このようなケースでは、まず「宗教」という言葉にとらわれず、事実関係の確認を最優先に行うことが必要です。
宗教や思想的な問題は、感情や誤解が入りやすい領域でもあり、依頼者様の認識が実態と異なっている可能性も十分に考えられます。
したがって、弊社ではまず「ご主人が現在どのような環境に身を置いているのか」「その背景に何があるのか」を確認するための調査と対象者への接触を提案しました。
面談時点で判明していたのは、ご主人がここ一年ほどで、職場での昇進見送りを経験していたということでした。
また、依頼者様によると、家にいてもほとんど仕事や将来の話をしなくなり、次第に自己否定的な発言が増えていったとのことです。
これらの情報から、弊社では「信仰の有無」よりも「心理的な変化の原因」に注目すべきだと考えました。
とはいえ、依頼者様が不安を抱いているのは宗教絡みという一点に集中していたため、その部分は尊重しつつ、まずは現状を把握するという立場を取りました。
提案の内容は、以下の三点になります。
第一に、夫である対象者の身辺調査です。
日常生活の中で、どのような人物や団体と関わりを持ち始めたのかを確認する。
勤務先から退勤後の交友関係・休日の過ごし方など、外部の影響がどの段階から強まったのかを具体的に把握します。
第二に、工作員に寄る接触です。
宗教団体に属している場合、外部の人間が不用意に踏み込むと目立つため、工作員はあくまで日常の延長線上で接触する形を取ります。
たとえば、仕事終わりに立ち寄る飲食店や書店など、対象者が警戒を示さない環境から自然に会話の糸口を作る。
そこでの発言内容や行動傾向をもとに、心理状態と環境要因を読み取ります。
第三に、依頼者様の自己改善です。
依頼者様が再会の場面で同じ誤解を繰り返さないようにする必要があります。
対象者が帰ってきたときに、責める側ではなく受け止める側として立てるよう準備しておくことが、この段階での最も重要な課題です。この部分においては工作員が接触して対象者の本心を知ってから始めましょうと提案しております。
宗教が関係している場合には、親族や周囲が巻き込まれることも少なくありません。
そのため、調査の進行と並行して、義両親を含めた家族全体の立ち位置を確認し、協力が得られる範囲を整理する方針も立てました。
対象者が外部の影響下にある場合、家庭内の支えを敵と感じさせないよう慎重に進める必要があります。
以上の提案を経て、依頼者様は「宗教という言葉に縛られず、まずは事実を知りたい」と考えを改められ、調査と接触の正式な依頼を決定されました。
この段階ではまだ、我々も宗教問題を前提とした調査を想定していましたが、実際に対象者へ接触を進めていく中で、後に大きな方向転換を迎えることとなります。
調査・工作の開始
調査開始からおよそ二週間後、対象者の生活圏に関する基礎的な情報が揃いました。
対象者は現在マンスリーマンションから出勤していることを確認しました。
勤務先の出勤状況には大きな変化は見られませんでした。
ただし、退勤後の行動パターンに顕著な変化が確認され、週に数回、特定の貸会議室ビルに立ち寄っていることが判明しました。
時間帯はおおむね19時から21時まで。入退出時の服装や荷物の様子からも、宗教的儀式のようなものではなく、セミナー形式の集まりである可能性が高いと推測されました。
この時点で我々は、対象者が実際にどのような集まりに関わっているのかを確認するため、現場に工作員を配置しました。
同ビル内で開催されていた講座の掲示や来訪者リストから、対象者が参加していたのは「自己成長をテーマにした人脈交流セミナー」であることが確認されました。
宗教団体としての届け出はなく、講師の個人名義で運営されており、会員の勧誘や教材販売を伴う半商業的な仕組みが見られました。
数回にわたり、男性工作員が対象者と同じセミナーに参加し、自然な形で会話を交わす機会を持ちました。
対象者は初対面に対しても社交的で、講師の話を熱心に聞く一方で、他の参加者との会話では「最近は会社の人間関係がうまくいかない」「それを家族に話しても理解はされないだろう」「家庭の中でも自分の居場所が分からなくなった」という発言が聞かれました。
宗教的な話題は一切なく、むしろ「ここでは前向きな人が多い」「救われる気がする」といった自己啓発的な表現が中心でした。
この結果から、我々は依頼者様が抱いていた「宗教にのめり込んでいる」という認識が誤りであることを確認することができました。
対象者は信仰心から行動しているのではなく、職場での停滞感や家庭での孤立感を埋めるために、自分を励ましてくれる場所を必要としていたと判断されます。
つまり、宗教ではなく心の依存先が変わったに過ぎないということです。
この報告を受け、依頼者様には現状を正確に伝えました。
当初は驚かれていましたが、【宗教ではなかった】という事実に安堵の表情を見せられました。
そのうえで、対象者が置かれている心理的状況。「家族の中で理解されない」「自分の努力が報われない」という点に対して、今後どのように関わるべきかを一緒に検討しました。
依頼者様もご自身の対象者に対する態度を振り返ると、ここ数年は子育てに一生懸命で対象者とゆっくり話をする機会もなかったとのこと。昇進が出来なかった際などは落胆した様子を見せてしまっていたかもしれないと話されていました。
以降の工作では、男性工作員を対象者のセミナー仲間という立ち位置で継続的に接触させ、対象者の発言や感情の変化を観察しました。
複数回の会話を通じ、対象者の口から「自分の勝手な意思で家を出てしまった」「もう家族や子どもに顔向けできない」という言葉が出始めました。これは、家庭に対する罪悪感が徐々に表面化してきた兆候と見られます。
この時点で、我々は依頼者様の行動修正フェーズに移行しました。
工作員の報告から、対象者が【後悔】や「許されたい」という感情を強く抱いていることが明確になったため、依頼者様には、対象者に「心配している」「子供が会いたがっている」ということが伝わるように、対象者のご両親や、共通の知人を通じて連絡を取るようにしましょう、と提案しました。
工作員の観測では、こうした間接的な変化を経て、対象者の表情や発言が少しずつ穏やかになり、セミナー内で「最近、気持ちが整理できてきた」という話をするようになりました。
次第にセミナーへの参加頻度も減少していったとのことです。
家庭への抵抗感を薄めるための準備が、確実に進んでいることが確認されました。
結末
調査開始からおよそ4カ月後、対象者の生活行動に明確な変化が見られました。
セミナーへの出席がなくなりました。
工作員からの報告では、自己啓発的な発言も減少し、家庭や仕事といった現実的な話題に興味を示すようになっているとのこと。
また、工作員との会話の中で対象者は「焦っても仕方ない」「結局、自分が逃げていた」といった言葉を口にするようになったとのことでした。
工作員はその変化を受け、これまでの活動を否定することなく、「家族の中での居場所を考えてみても良いのではないか」「家族と話してみてはどうか」という話題を自然に挟むようにしました。
対象者は明確な返答を避けながらも、家族との関係を意識している様子が見られました。
この段階で、弊社は依頼者様に再会のタイミングについての提案を行いました。
対象者が罪悪感を抱えている段階で強い呼びかけを行うと、再び逃避行動に出るリスクがあるため、あくまで自然な再接点の演出を目的としました。
再度、共通の友人を通じて、子どもの近況をさりげなく伝えてもらう形を取り、対象者の中に【家族としての現実】を思い出させる導線を設置しました。
数週間後、対象者から依頼者様宛に短いメッセージが届きました。
「子どもに会いたい」との一言だけでしたが、この連絡が本件における最初の転機となりました。
依頼者様は弊社の助言に沿って、直接的な説得を避け、落ち着いてやり取りを重ねられました。
ついに子どもと食事をする約束をきっかけに、対象者は数か月ぶりに自宅に帰宅しました。
この再会を通じて、【家庭が自分を否定する場所ではない】と再確認されたようで、以降は週末ごとに子どもに会いに帰宅するようになりました。
その過程で依頼者様から対象者にも、これまで子供だけに意識が向いていて、【対象者に寄り添えていなかったこと】を後悔していると伝えたようです。
しばらくしてお互いのわだかまりがなくなっていったようで、やがて再同居に向けた話し合いが始まり、依頼者様から「一緒に生活を戻す準備を始めています」との報告を受けました。
その後に、依頼者様と対象者は正式に同居を再開。
家庭内の会話や生活リズムも徐々に安定し、依頼者様からは「以前のような暮らしが戻りつつある」との報告を受けています。
今回の案件から得られた教訓は、宗教や信仰といった外面的な要素だけに注目すると、問題の本質を見誤るということです。
対象者が求めていたのは教義ではなく、自分自身が理解される場所でした。
そしてその理解は、依頼者様自身が変わることで初めて再び家庭の中に生まれたと言えます。
復縁とは、相手を変えさせる行為ではなく、相手が戻りたいと思える環境を整えることである。
本案件は、その原則を最も象徴的に示したケースの一つとなりました。
参考記事:価値観の違いで別れたカップルは復縁できる?
参考記事:復縁工作:価値観の違いで別れてしまったカップルの復縁
参考記事:復縁工作:価値観のズレで振られてしまった状況からの復縁
参考記事:復縁工作:夫に離婚を突然突き付けられました、復縁を望んでいます
参考記事:突然家出をした夫と関係を修復したい
参考記事:復縁工作:出て行った旦那と子供と、また一緒に暮らしたい
参考記事:復縁したいなら相手の両親を味方につけましょう