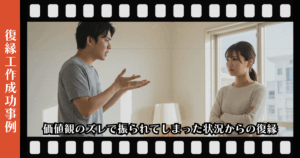復縁屋ハートリンクで実際に対応した案件の一部を、依頼者様のご了承をいただいたうえで掲載しています。なお、プライバシー保護のため、内容の一部は編集を加えております。
| 工作種別 | 復縁工作 |
|---|---|
| 依頼者情報 | 千葉県在住38歳 女性 |
| 対象者情報 | 千葉県在住39歳 男性 |
| 契約期間 | 4カ月 |
参考記事:復縁診断|復縁したい!あなたの復縁の可能性を測ります。
ご相談
今回ご相談に来られたのは、30代後半の女性でした。
依頼者様は結婚して10年以上が経ち、小学生の子どもが一人いらっしゃいます。
現在は夫と別居中で、子どもは夫のもとで生活しているとのことでした。
依頼者様は、別居に至るまでの経緯を話されました。
もともと夫婦共働きで、依頼者様は会社で責任ある立場を任されており、仕事を優先せざるを得ない生活が続いていたそうです。
家事や育児の多くは夫が担い、休日もそれぞれ別々に過ごすことが増えていったと話されました。
依頼者様自身は「家族のために働いていた」という意識が強く、家庭をないがしろにしていたという自覚は当初なかったそうです。
しかし、夫の様子が少しずつ変化し始めたといいます。
以前はよく話しかけてくれていたのに、会話が減り、休日も外出が増え、家にいる時間が短くなっていったとのことでした。
子どもの学校行事や食事の準備なども、いつの間にか夫が主導するようになり、「気づけば、夫と子どもが二人で家庭を回していた」と依頼者様は振り返られました。
別居を告げられたのは半年前だったそうです。
ある日、夫から「もう一緒にいる意味が分からない」と言われ、そのまま荷物をまとめて出て行かれたとのことでした。その際、夫は怒りを見せることもなく、淡々としていたそうで、依頼者様は「もう自分に対する感情が何も残っていないように見えた」と語られました。
その後、夫のご両親に連絡を取ったものの、「彼はよく我慢していたと思う」「今さら何を言っても遅い」などの反応があり、親族全体が夫の側に立っていることを感じたといいます。
依頼者様の実家の両親からも「あなたが悪かったのではないか」と言われ、味方がいない心境になっている様子がうかがえました。
依頼者様はご相談の中で、「夫の怒りを買うようなことはしていないのに、なぜここまで拒絶されるのか分からない」「浮気をしているわけでもないのに、どうして家庭が壊れてしまったのか」
と繰り返し口にされていました。
一方で、仕事を優先してきた自分の生き方が、結果的に夫や子どもを追い詰めた可能性も感じていると話されました。
現在は夫との連絡はほとんど取っておらず、子どもについての必要最低限のやり取りだけが続いている状況です。
依頼者様としては、離婚届はまだ提出されていないため、「もう一度やり直せるなら何とかしたい」というお気持ちでご相談に来られました。
ただし、具体的に何から始めればよいのか分からず、夫の考えや現状を知る手段がないことに不安を抱いておられました。
面談・提案
面談では、依頼者様からさらに詳しくお話を伺いました。
結婚当初から現在に至るまでの家庭状況、別居に至る前後の夫の行動、そしてお二人のやり取りについて、記録やLINEの履歴を確認しながら整理を行いました。
依頼者様の話によると、夫婦関係が悪化し始めたのは2年ほど前からだそうです。
依頼者様は仕事の繁忙期が続き、帰宅が遅くなることが多かったとのことでした。
その間、子どもの送迎や夕食の準備などはすべて夫が行っていたようで、依頼者様自身は「感謝していたつもり」だったと話されましたが、実際に言葉や態度で伝える機会はほとんどなかったと確認できました。
LINEの履歴を拝見すると、夫からの連絡は「今日は遅くなる?」「明日の予定は?」といった事務的な内容が中心で、会話らしいやり取りはほとんどありませんでした。
また、依頼者様の返信も「仕事が終わらない」「後で話す」といった短文が多く、夫からの問いかけが途切れるように終わっているケースが複数見られました。
これらのやり取りからは、夫が徐々に会話の必要性を感じなくなっていった経緯がうかがえます。
別居前には、夫から「この生活を続ける意味がない」と言われたと依頼者様は話されましたが、そこに強い怒りや感情的な要素はなく、むしろ淡々としていたとのことでした。
このことから、夫がすでに感情的な衝突ではなく、理性的な判断として別居を選んだ可能性が高いと考えられます。
つまり、感情の爆発ではなく「冷めきった結論」に至っている可能性があるため、単なる謝罪や反省だけでは関係が戻りにくい状況だと判断しました。
また、依頼者様は「夫が浮気をしている様子はない」と明言されましたが、実際には休日の外出先や人間関係について把握できておらず、この点については客観的な確認が必要と考えました。
夫がどのような環境に身を置き、どのような交友関係を築いているのかを把握することで、「別居後の生活が安定しているのか」あるいは「誰か特定の存在に支えられているのか」を明確にできます。
これにより、今後の行動方針を誤らないための判断材料が得られます。
以上の情報を踏まえ、現段階での提案は以下の通りです。
まず、対象者である夫の生活状況を把握することが最優先となります。
現在の居住先、勤務状況、交友関係、休日の過ごし方などを確認し、新たな人間関係の有無を調べることで、別居後の心理的な変化を読み解くことができます。
この調査によって、夫が「離婚」という選択を現実的に進めているのか、あるいは「時間を置くことで整理しようとしているのか」を判断する材料が得られます。
次に、依頼者様ご自身の生活改善についても整理しました。
依頼者様は「家庭を顧みなかった」と何度も口にされていましたが、その言葉の裏には「どうすれば取り戻せるのか分からない」という戸惑いが見られました。
そこで、今後は仕事中心の生活を少しずつ見直し、子どもとの時間を増やすこと、家事に関わる習慣を取り戻すことを具体的な行動目標としました。
これは単なる“反省”ではなく、夫が感じていた家庭内での損失を埋めるための行動として位置づけています。
夫が離れた理由が「無関心」であれば、逆に「変化が目に見える行動」を示すことが、最も効果的な第一歩になります。
また、両家の関係修復についても触れました。
夫のご両親との関係悪化は、夫婦間のわだかまりを固定化させる要因になります。
そのため、依頼者様が直接関わるのではなく、子どもを介して交流の場を設けることを提案しました。
たとえば、子どもの学校行事や誕生日など、自然な形で接点を増やし、依頼者様の変化が家族内で伝わるように環境を整えることを目的とします。
調査を通じて得られる客観的な情報を基に、次の段階では工作員による接触計画を検討し、夫の現実的な判断基準(何を得たいか・何を守りたいか)を特定していきます。
依頼者様には、焦らずに行動を継続していただき、夫が「今の彼女は変わった」と感じられるだけの“環境の変化”を整えることが必要であるとお伝えしました。
調査・工作の開始
調査は、対象者である夫の現状把握から始まりました。
勤務先は依頼者様から伺っていた情報と一致しており、別居後も職場環境や通勤時間等に変化は確認されませんでした。
平日は朝に子どもを学校まで送り、下校後は学童保育を利用している様子が確認されています。
夫は仕事を終えると概ね19時前後に帰宅し、近隣のスーパーで買い物をしてから自宅へ戻ることが多く、夕食や就寝までの時間を子どもと共に過ごしている状況が見られました。
休日は自宅近くの公園で子どもと過ごす姿が確認され、特に午前中から昼にかけての滞在が多く、その際には夫の両親と思われる人物が一緒にいることもありました。
子どもとの関係は良好であり、家族としての生活基盤を夫側が中心に維持している様子が見て取れました。
この観測結果から、夫は「新しい生活」を築くよりも、子どもを中心に安定した家庭環境を保つことを優先していると判断しました。
家庭を否定する意図ではなく、妻との関係を除いた形での再構築を進めている状態といえます。
このため、直接的な接触は不自然であり、むしろ抵抗感を強めるリスクが高いと判断しました。
そこで弊社では、対象者本人ではなく義両親を媒介とした間接的な接触を計画しました。
調査の段階で、夫の両親が地域の清掃活動や学校行事に定期的に参加していることが確認されており、この地域活動を自然な接点として活用することを決定しました。
接触には、対象者と同年代の男性工作員を選定し、地域ボランティアとして義両親の生活圏に関わる形でアプローチを開始しました。
初期の接触は、地域の清掃活動における作業の分担から始まりました。
工作員は、以前同地区で暮らしていたという設定で参加しており、学校行事や地域の子どもに関する話題を自然に取り入れながら、世間話を交わせる距離感を慎重に作りました。
挨拶や短い会話を繰り返すうちに、義母からも声をかけられるようになり、「この辺りは子育てがしやすい」「最近は若い人が増えた」などの会話が成立するようになりました。
2回目以降の接触では、工作員が自身の家庭について触れる場面を作りました。
「うちも数年前に夫婦の間がうまくいかなくて、一度は別居したことがあった」と話し、そのときに子どもが母親の不在を強く感じていた様子を静かに語りました。
「父親が一生懸命でも、やっぱり子どもは母親がいないと心の奥で寂しいようで」といった一言が、義母の関心を引くきっかけになりました。
この会話の流れの中で、義母が自ら息子夫婦の別居に触れました。
「うちの息子も似たようなところがあってね」「子どものために我慢しているけれど、あの子(依頼者様)は頑張り方が少し違ったのよ」
という趣旨の発言があり、義母が依頼者様を完全に否定しているわけではなく、むしろ認めたいが素直に受け入れられない状態であることが見えてきました。
この段階で、工作員は「家族の話題を義母の口から自然に出させること」に成功しています。
弊社では、この発言を義両親の印象が硬直から揺らぎ始めた初期反応と判断しました。
この情報を踏まえ、弊社では義両親の印象転換を先行させる方針に切り替えました。
依頼者様には、直接謝罪や弁明を試みるのではなく、子どもを通じて小さな感謝の行動を積み重ねるよう指導しました。
たとえば、子どもの誕生日や学校行事の際に「いつもありがとうございます」と短いメッセージを添えた差し入れを行うなど、形式的でも誠実な姿勢が伝わる形に整えました。
これにより、義両親が「変わろうとしている」「以前と違う」と受け取る状況を作り出しました。
数週間後、工作員からの報告で、義母が地域の知人に対して「嫁が気を使って差し入れをしてくれている」と話す場面が確認されました。
この発言は、義両親の印象が軟化し始めた兆候であり、家庭内の空気がわずかに変わり始めたことを示しています。
依頼者様にも報告を共有し、焦らず行動を継続していただくよう助言しました。
弊社ではこの段階を、対象者の拒絶が家族単位で緩み始めた初期フェーズと捉えています。
今後は、義両親との関係を安定させながら、夫が「家族としての再統合」を現実的に考えられる環境を整える方向で進行していく予定です。
結末
義両親を通じた印象改善の取り組みを継続してから約3か月後、工作員より「義母が依頼者様について前向きな発言をするようになった」との報告が入りました。
その内容は、「最近は以前より落ち着いた」「子どもとの関わりを見直しているようだ」というものです。
この時点で、義両親の間で依頼者様に対する拒絶が様子見へと移行したと判断しました。
さらにその数週間後、依頼者様から「夫から子どもの学校行事の件で連絡が来た」と報告を受けました。
以前であれば連絡は事務的なLINEのみでしたが、このときは「その日空いてる? 一緒に行けそうなら子どもも喜ぶと思う」といった、協力を求める柔らかい内容だったとのことでした。
行事当日、夫と依頼者様は短時間ながら自然な会話を交わし、子どもを中心に再び家族としての時間を共有することができました。
弊社では、今回の再会を偶然ではなく環境変化の結果と位置づけています。
義両親の態度が軟化したことで、夫の心理的防御が家族単位で緩み、「拒絶を貫く必要がなくなった」ことが接触の再開に繋がったと分析しています。
夫自身が依頼者様を感情的に許したというより、「子どもにとっての母親としての存在を再評価した」結果であり、
これは家庭再構築の初期段階における極めて重要な兆候です。
その後も、子どもの学校行事や日常のやり取りを通じて、依頼者様と対象者の会話は少しずつ増えていきました。
依頼者様からの報告では、「今は一緒に暮らす話までは出ていませんが、連絡が普通にできる関係に戻れたことが何より嬉しい」との言葉がありました。「ここまで来れれば後は大丈夫です。本当にありがとうございました」との依頼者様からのお言葉で、本案件を終了といたしました。
復縁は、感情だけでも、理屈だけでも成り立ちません。
人が関係を戻すとき、その裏には「納得」という感情がある。
それは愛情や情だけでなく、「この人とならもう一度やっていける」という、感情と理屈が交わる地点です。
私たちが整えるのは、その納得が生まれる現実です。
たとえば、子どもと笑う依頼者様の姿を見たとき、ふと「この形が一番自然かもしれない」と感じる瞬間。それが、感情と理屈が並ぶ場所です。
感情を無理に動かすのではなく、自然と心が戻る環境を作る。
それが、復縁屋ハートリンクの復縁屋工作です。
参考記事:復縁工作:夫に離婚を突然突き付けられました、復縁を望んでいます
参考記事:突然家出をした夫と関係を修復したい
参考記事:復縁工作:浮気をして振ってしまった元夫と復縁したい
参考記事:復縁したいなら相手の両親を味方につけましょう